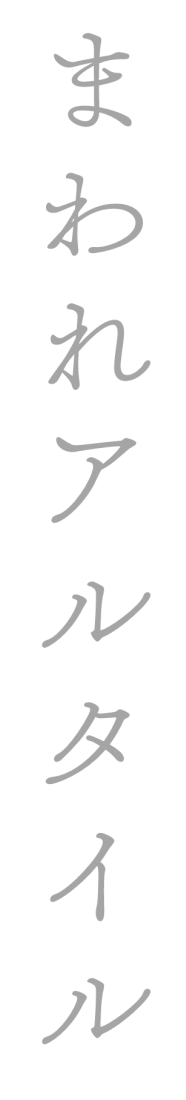
懐かしいものが出てきた。
みずのごようになりたい。
古びて黄ばんだ資料の間からひらりと落ちたのは、幼いながら勢いのある字でそう書かれた短冊一枚。道場に色とりどりの飾りをつるした笹を飾っていたのは何年前までだっただろう、と手にとったそれを見つめながら吹雪は記憶をたぐる。もうずいぶんと昔のことだ。今年はその日が過ぎたことすら気づかなかった。
立ち上がって庭に面した障子をあける。夜風が肌にしみた。あいにくと雲が多くて星はその合い間にしか見えない。
「風邪、ひきますよ」
黒衣の友人が文机に向かったまま抑揚のない声で言った。
吹雪が風邪をひいたことなどもう何百年もない、それはひしぎも知っている。暑かろうが寒かろうがなんの関係もないような顔をしている彼に短冊を示してみせると、受けとってしばらくそれを眺め、ああ、と頷いた。
「それで、星を?」
吹雪も頷いた。風がつめたい。壬生の短い夏はもう半ばを過ぎていた。
ひしぎはまだ手の中の短冊を見ている。
「……辰伶の願いは、叶ったんですね」
それは皮肉のようにも聞こえた。
五曜星への昇進が決まったときの弟子の顔が浮かんだ。誇らしげな、とても誇らしげな、笑み。あのまっすぐな誇りと信頼を裏切らねばならない日がくることを思うと胸に重いものが沈むのを吹雪は感じた。決して躊躇するつもりはない、切り捨てることにはもう慣れている。けれどなんの感情も伴わずにできることでもなかった。
別れというのはもう二度と会うことができないということだ。今まで別れたものも、これから別れるものも。一年に一度まみえることができるならそれに何の不満があるだろう。
気がすんだのか、ひしぎが吹雪に短冊を手渡す。ひしぎはこういう時決して左手を使わない。漆黒の革に包まれたその指を、見るともなしに吹雪は見る。
「……もし叶うとしたら、お前は何を願う」
ほんの薄い興味からぽろりと口にしただけだったのだが、そのとたん驚いたように見ひらかれたひしぎの隻眼に吹雪のほうが面食らった。
「……わかりませんか」
さも心外そうにひしぎが訊く。
「わからんな」
「本当ですか」
「だからわからんと言っている」
「本当に?」
「しつこいぞ、ひしぎ」
ごく小さく肩をすくめるような仕草をしてみせてひしぎは黙った。やがて夜が更けて、持ち帰る分の仕事を片腕にかかえた彼が立ち上がるまでその静寂はつづいた。
「そろそろ戻ります」
「ああ」
応えながら吹雪が視線を持ちあげると、障子戸に手をかけたひしぎがちょうど振り返ったところだった。
眼が合った。
「……あなたののぞみが、かないますように」
とん、と軽い音をたてて戸が閉まった。
<<
みずのごようになりたい。
古びて黄ばんだ資料の間からひらりと落ちたのは、幼いながら勢いのある字でそう書かれた短冊一枚。道場に色とりどりの飾りをつるした笹を飾っていたのは何年前までだっただろう、と手にとったそれを見つめながら吹雪は記憶をたぐる。もうずいぶんと昔のことだ。今年はその日が過ぎたことすら気づかなかった。
立ち上がって庭に面した障子をあける。夜風が肌にしみた。あいにくと雲が多くて星はその合い間にしか見えない。
「風邪、ひきますよ」
黒衣の友人が文机に向かったまま抑揚のない声で言った。
吹雪が風邪をひいたことなどもう何百年もない、それはひしぎも知っている。暑かろうが寒かろうがなんの関係もないような顔をしている彼に短冊を示してみせると、受けとってしばらくそれを眺め、ああ、と頷いた。
「それで、星を?」
吹雪も頷いた。風がつめたい。壬生の短い夏はもう半ばを過ぎていた。
ひしぎはまだ手の中の短冊を見ている。
「……辰伶の願いは、叶ったんですね」
それは皮肉のようにも聞こえた。
五曜星への昇進が決まったときの弟子の顔が浮かんだ。誇らしげな、とても誇らしげな、笑み。あのまっすぐな誇りと信頼を裏切らねばならない日がくることを思うと胸に重いものが沈むのを吹雪は感じた。決して躊躇するつもりはない、切り捨てることにはもう慣れている。けれどなんの感情も伴わずにできることでもなかった。
別れというのはもう二度と会うことができないということだ。今まで別れたものも、これから別れるものも。一年に一度まみえることができるならそれに何の不満があるだろう。
気がすんだのか、ひしぎが吹雪に短冊を手渡す。ひしぎはこういう時決して左手を使わない。漆黒の革に包まれたその指を、見るともなしに吹雪は見る。
「……もし叶うとしたら、お前は何を願う」
ほんの薄い興味からぽろりと口にしただけだったのだが、そのとたん驚いたように見ひらかれたひしぎの隻眼に吹雪のほうが面食らった。
「……わかりませんか」
さも心外そうにひしぎが訊く。
「わからんな」
「本当ですか」
「だからわからんと言っている」
「本当に?」
「しつこいぞ、ひしぎ」
ごく小さく肩をすくめるような仕草をしてみせてひしぎは黙った。やがて夜が更けて、持ち帰る分の仕事を片腕にかかえた彼が立ち上がるまでその静寂はつづいた。
「そろそろ戻ります」
「ああ」
応えながら吹雪が視線を持ちあげると、障子戸に手をかけたひしぎがちょうど振り返ったところだった。
眼が合った。
「……あなたののぞみが、かないますように」
とん、と軽い音をたてて戸が閉まった。
<<