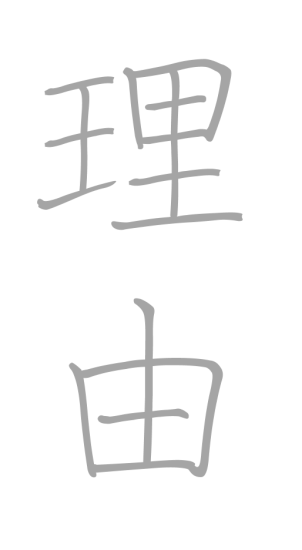
ひとつの疑問があった。長年にわたる疑問が。
ひしぎはなぜここにいるのか。
彼の言う地獄への道を無理に強いたつもりはないと、遠慮せず出ていけと、吹雪は何度もそう告げている。しかし彼は頑として首を縦に振らない。
わからない。
お前は、なぜ、ここにいるのか。
「ですから、私はあなたにどこまでもついていくとあの時」
「その台詞はもういい。聞き飽きた」
吹雪の強い口調にひしぎが黙った。視線が宙を迷う。
「どうしても、言わなければいけませんか」
吹雪は頷く。知りたい。本当のことが。
相手の変わらぬ意志を受けて、ひしぎがふ、と息をついた。
「……どうやら、真実を打ち明けねばならないときが来てしまったようですね……」
沈痛な面持ちで彼は吹雪を見る。
「本当は、一生口にするつもりはなかったのですが……いいでしょう。すべて話します。私がここにいる、理由を」
追憶のまなざしでひしぎは語りはじめ、固唾を呑んで吹雪はそれを見守る。
「あなたは憶えていないかもしれませんが、私は片時たりとも忘れたことはありません。あれは遠い昔の、ある冬の日のことでした。あの日、不注意から罠にかかって動けずにいた私は、降りしきる雪に半ば埋もれて飢えと寒さで意識を失いかけていました。ぼんやりとしかし確実に死を覚悟した私を、たまたまそこに通りかかったあなたが罠から救い出し、手当てを施してくれたのです。そのおかげで私は再び飛び立つことができました。そう、私は、私はもともと壬生一族ではありません。あの日あなたに助けられた、一羽の鶴なのです」
「……」
「そして月日は流れ、壬生一族になりすました私は太四老の地位までのぼりつめました。すべてはあの日、私の命を救ってくれたあなたの恩に報いるために。ちなみに本来の伝統に沿うならばここは布を織るべきところなのですが、その方面は不得手なものであきらめました。ですからせめて太四老としてあなたの役に立ちたかったのです。しかし真実を知られてしまった以上、ここに留まることはできません。掟に従い故郷の山に帰ります。さようなら吹雪、今まで本当にありが」
「ひしぎ」
言外にふざけるのはよせという非難を含ませた吹雪の声に、すみません冗談です、とひしぎが首をすくめる。
「それでは本当のことを話しましょう。あなたは憶えていないかもしれませんが、前世での我々は、私があなたを死ぬまで必ず守り抜くと固く契約した間柄でした。しかし、いかんともしがたい諸事情によって互いの道は分かたれ、その契約は果たせなかったのです」
「……なんだ、その諸事情とは」
「まあ、いろいろです」
「適当だな」
「そして今生で運命的に再び巡り会えたあなたを今度こそ私は」
「ひしぎ」
「すみません、冗談です」
ひしぎの切り替えは早い。
「それでは改めて本当のことを話しましょう。 実は私は、壬生と同等の力を持ち今まさにこれを打ち滅ぼさんとする敵国から、あなたを殺害するために送り込まれた刺客だったのです」
「……どこにそんな敵国があるのだ、どこに」
「機密ですのでそれは言えません。本国から派遣された私は首尾よく壬生の中枢へ入りこみ、日々何気ない顔をして標的であるあなたのそばで暮らしながら計画を練り、その首を掻っ切る機会をうかがっていたのです。しかしそれももはやここまで。あなたに恨みはありませんが、上からの指令に逆らうこともできません。太四老吹雪、覚悟。お命頂戴仕ります」
「ひしぎ」
「すみません、冗談です」
実際に抜刀しかけていたひしぎが、かちんと鍔を鳴らして刃を納めた。
「恩返しも前世も暗殺計画もありません。今度こそ真実を言わせてもらうと、あなたは私の友人です」
「そうだろうな」
梅雨の晴れ間の午後だった。彼の背後で障子に色濃く落ちた青葉の影が揺れている。
「そんな相手が困っていたら助けたいと、哀しんでいたら支えたいと、願いがあれば叶えたいと、そう思うのはおかしいことでしょうか」
風が鳴る。
無数の葉が擦れる音。その中にくっきりと浮かび上がるひしぎの声。
「私がここにいることに、それ以上の理由が必要ですか」
片方しかない彼の瞳が真摯な光を宿して吹雪を見つめる。
胸の痛むような思いで、吹雪はそれを見返す。
「……ひしぎ」
喉の奥が詰まる。
「ひしぎ、俺は……」
「今回は疑いもしないのですか?」
急速に冷えた口調でひしぎがぴしゃりと遮った。
「この手の話をあまり鵜呑みにしないでくださいね、吹雪」
まっすぐに吹雪を刺す視線にも、先程までの温度はもう見当たらない。
「……あなたのそういう甘いところ、時々心配になります」
少しだけ柔らかくつけ加えてくるりと踵を返すその背を、吹雪は何も言えずに見送る。
――失敗した。
足早に廊下を歩くひしぎの胸にはひとつの決意がある。
――言葉で説明できるようなことではなかったのだ。
あの日誓ったこと、友に寄り添いたいという思い、研究者としての責任。あるいは村正の頼み、姫時の遺志、子らの涙。失われた過去、あったはずの未来、真の一族への憎悪。それらにすべてを帰結させるのは容易だ。それでも、口にすれば欠けてしまう何かがある。
言うべきではなかった。少なくとも今ではなかった。
それでも。
それでも、いつかは伝えよう。
理由も動機もなく、誓いも約束も超えて、ただ、ここにいたかったのだと。
<<
ひしぎはなぜここにいるのか。
彼の言う地獄への道を無理に強いたつもりはないと、遠慮せず出ていけと、吹雪は何度もそう告げている。しかし彼は頑として首を縦に振らない。
わからない。
お前は、なぜ、ここにいるのか。
「ですから、私はあなたにどこまでもついていくとあの時」
「その台詞はもういい。聞き飽きた」
吹雪の強い口調にひしぎが黙った。視線が宙を迷う。
「どうしても、言わなければいけませんか」
吹雪は頷く。知りたい。本当のことが。
相手の変わらぬ意志を受けて、ひしぎがふ、と息をついた。
「……どうやら、真実を打ち明けねばならないときが来てしまったようですね……」
沈痛な面持ちで彼は吹雪を見る。
「本当は、一生口にするつもりはなかったのですが……いいでしょう。すべて話します。私がここにいる、理由を」
追憶のまなざしでひしぎは語りはじめ、固唾を呑んで吹雪はそれを見守る。
「あなたは憶えていないかもしれませんが、私は片時たりとも忘れたことはありません。あれは遠い昔の、ある冬の日のことでした。あの日、不注意から罠にかかって動けずにいた私は、降りしきる雪に半ば埋もれて飢えと寒さで意識を失いかけていました。ぼんやりとしかし確実に死を覚悟した私を、たまたまそこに通りかかったあなたが罠から救い出し、手当てを施してくれたのです。そのおかげで私は再び飛び立つことができました。そう、私は、私はもともと壬生一族ではありません。あの日あなたに助けられた、一羽の鶴なのです」
「……」
「そして月日は流れ、壬生一族になりすました私は太四老の地位までのぼりつめました。すべてはあの日、私の命を救ってくれたあなたの恩に報いるために。ちなみに本来の伝統に沿うならばここは布を織るべきところなのですが、その方面は不得手なものであきらめました。ですからせめて太四老としてあなたの役に立ちたかったのです。しかし真実を知られてしまった以上、ここに留まることはできません。掟に従い故郷の山に帰ります。さようなら吹雪、今まで本当にありが」
「ひしぎ」
言外にふざけるのはよせという非難を含ませた吹雪の声に、すみません冗談です、とひしぎが首をすくめる。
「それでは本当のことを話しましょう。あなたは憶えていないかもしれませんが、前世での我々は、私があなたを死ぬまで必ず守り抜くと固く契約した間柄でした。しかし、いかんともしがたい諸事情によって互いの道は分かたれ、その契約は果たせなかったのです」
「……なんだ、その諸事情とは」
「まあ、いろいろです」
「適当だな」
「そして今生で運命的に再び巡り会えたあなたを今度こそ私は」
「ひしぎ」
「すみません、冗談です」
ひしぎの切り替えは早い。
「それでは改めて本当のことを話しましょう。 実は私は、壬生と同等の力を持ち今まさにこれを打ち滅ぼさんとする敵国から、あなたを殺害するために送り込まれた刺客だったのです」
「……どこにそんな敵国があるのだ、どこに」
「機密ですのでそれは言えません。本国から派遣された私は首尾よく壬生の中枢へ入りこみ、日々何気ない顔をして標的であるあなたのそばで暮らしながら計画を練り、その首を掻っ切る機会をうかがっていたのです。しかしそれももはやここまで。あなたに恨みはありませんが、上からの指令に逆らうこともできません。太四老吹雪、覚悟。お命頂戴仕ります」
「ひしぎ」
「すみません、冗談です」
実際に抜刀しかけていたひしぎが、かちんと鍔を鳴らして刃を納めた。
「恩返しも前世も暗殺計画もありません。今度こそ真実を言わせてもらうと、あなたは私の友人です」
「そうだろうな」
梅雨の晴れ間の午後だった。彼の背後で障子に色濃く落ちた青葉の影が揺れている。
「そんな相手が困っていたら助けたいと、哀しんでいたら支えたいと、願いがあれば叶えたいと、そう思うのはおかしいことでしょうか」
風が鳴る。
無数の葉が擦れる音。その中にくっきりと浮かび上がるひしぎの声。
「私がここにいることに、それ以上の理由が必要ですか」
片方しかない彼の瞳が真摯な光を宿して吹雪を見つめる。
胸の痛むような思いで、吹雪はそれを見返す。
「……ひしぎ」
喉の奥が詰まる。
「ひしぎ、俺は……」
「今回は疑いもしないのですか?」
急速に冷えた口調でひしぎがぴしゃりと遮った。
「この手の話をあまり鵜呑みにしないでくださいね、吹雪」
まっすぐに吹雪を刺す視線にも、先程までの温度はもう見当たらない。
「……あなたのそういう甘いところ、時々心配になります」
少しだけ柔らかくつけ加えてくるりと踵を返すその背を、吹雪は何も言えずに見送る。
――失敗した。
足早に廊下を歩くひしぎの胸にはひとつの決意がある。
――言葉で説明できるようなことではなかったのだ。
あの日誓ったこと、友に寄り添いたいという思い、研究者としての責任。あるいは村正の頼み、姫時の遺志、子らの涙。失われた過去、あったはずの未来、真の一族への憎悪。それらにすべてを帰結させるのは容易だ。それでも、口にすれば欠けてしまう何かがある。
言うべきではなかった。少なくとも今ではなかった。
それでも。
それでも、いつかは伝えよう。
理由も動機もなく、誓いも約束も超えて、ただ、ここにいたかったのだと。
<<