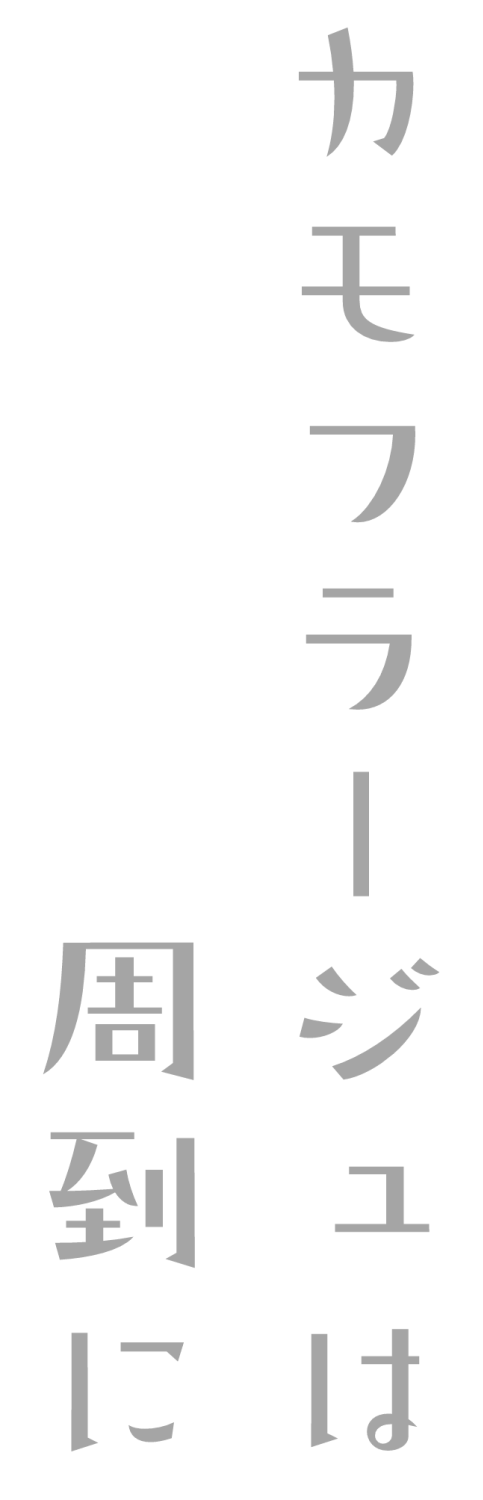
村正が蕎麦を打っている。
軽妙な手つきは習いはじめてたった半月の素人にはとても見えない。見守っている吹雪の前で、ただの粉だったものがどんどんと姿をかえていく。袖をまくり髪をくくり、台上の生地と向き合う村正は殺気に似たものすら漂わせている。こねる。こねる。のばす。のばす。そして切る。
恐るべき速度と完璧な等間隔で端から生地が裁断されていくさまは、なんというか、美しかった。蕎麦生地に対する形容としてはどうかと思うが。
あっという間に麺のかたちをなしたそれが沸騰する湯にするりと投入され、鍋の中で陽気な生きもののように踊る。
「吹雪」
鍋の前で菜箸片手に村正が言った。
「山葵のすりおろし、頼んでもいいですか?」
「下ろし金は」
「右上の棚です」
彼の声がいきいきと弾んでいる。すっきり整頓された村正宅の台所で、吹雪はその場所に手をのばす。
遅めの昼食である。ずる、と軽く音をたてて村正が蕎麦をすする。吹雪が顔をしかめてみせると、「たまにこういう食べ方してみたくなりませんか」と笑う。
村正はこのところ、老後の生きがい探しと称してありとあらゆる趣味に手を出していた。
吹雪は自分の前の蕎麦猪口を見る。
「……この前は確か」
「盆栽です」
「その前が」
「川釣りですね。陶芸はそのもうひとつ前」
土をこね回し華麗にろくろを操り染付までひと通り習得して、満足した風で村正はそれから離れたのだ。次に釣り。そして盆栽。それから蕎麦。しかしその全部が、吹雪には何かの伏線のように思えてならないのだった。半年前に作られた蕎麦猪口が、今まさにこうして使われているように。
考えながら吹雪は箸を動かす。井戸水で冷やしてあった麺つゆの温度が舌にこころよい。
「自分で言うのもなんですけど、なかなかのものだと思いません?」
確かに、香りといい歯ごたえといい喉ごしといい、文句のつけようのない出来だった。吹雪は意識の表面にその感想を押し出す。勝手に読め。
「でしょう」
黙したままの吹雪の意図を理解して能力を発動させたらしい村正が微笑む。
「粉にはこだわりましたから。あとは、ちょっと道具にも凝ってみたりして。麺棒なんかわざわざ上方から取り寄せたんですよ」
「……よくもそこまでできるものだな」
趣味らしい趣味を持たぬ吹雪には理解しがたい。
「私は弘法じゃないので筆は選びます。でも、たとえ弘法であっても選んだほうがいいと思うんですよね。道具は大事ですから。いい筆、使わないと」
(いい筆、作らないと)
「次は何をする気だ」
「そうですね、次は」
一瞬消えていた笑みをさりげなく浮かべなおして、村正が言う。
「刀鍛冶でも習いましょうかねえ」
<<
軽妙な手つきは習いはじめてたった半月の素人にはとても見えない。見守っている吹雪の前で、ただの粉だったものがどんどんと姿をかえていく。袖をまくり髪をくくり、台上の生地と向き合う村正は殺気に似たものすら漂わせている。こねる。こねる。のばす。のばす。そして切る。
恐るべき速度と完璧な等間隔で端から生地が裁断されていくさまは、なんというか、美しかった。蕎麦生地に対する形容としてはどうかと思うが。
あっという間に麺のかたちをなしたそれが沸騰する湯にするりと投入され、鍋の中で陽気な生きもののように踊る。
「吹雪」
鍋の前で菜箸片手に村正が言った。
「山葵のすりおろし、頼んでもいいですか?」
「下ろし金は」
「右上の棚です」
彼の声がいきいきと弾んでいる。すっきり整頓された村正宅の台所で、吹雪はその場所に手をのばす。
遅めの昼食である。ずる、と軽く音をたてて村正が蕎麦をすする。吹雪が顔をしかめてみせると、「たまにこういう食べ方してみたくなりませんか」と笑う。
村正はこのところ、老後の生きがい探しと称してありとあらゆる趣味に手を出していた。
吹雪は自分の前の蕎麦猪口を見る。
「……この前は確か」
「盆栽です」
「その前が」
「川釣りですね。陶芸はそのもうひとつ前」
土をこね回し華麗にろくろを操り染付までひと通り習得して、満足した風で村正はそれから離れたのだ。次に釣り。そして盆栽。それから蕎麦。しかしその全部が、吹雪には何かの伏線のように思えてならないのだった。半年前に作られた蕎麦猪口が、今まさにこうして使われているように。
考えながら吹雪は箸を動かす。井戸水で冷やしてあった麺つゆの温度が舌にこころよい。
「自分で言うのもなんですけど、なかなかのものだと思いません?」
確かに、香りといい歯ごたえといい喉ごしといい、文句のつけようのない出来だった。吹雪は意識の表面にその感想を押し出す。勝手に読め。
「でしょう」
黙したままの吹雪の意図を理解して能力を発動させたらしい村正が微笑む。
「粉にはこだわりましたから。あとは、ちょっと道具にも凝ってみたりして。麺棒なんかわざわざ上方から取り寄せたんですよ」
「……よくもそこまでできるものだな」
趣味らしい趣味を持たぬ吹雪には理解しがたい。
「私は弘法じゃないので筆は選びます。でも、たとえ弘法であっても選んだほうがいいと思うんですよね。道具は大事ですから。いい筆、使わないと」
(いい筆、作らないと)
「次は何をする気だ」
「そうですね、次は」
一瞬消えていた笑みをさりげなく浮かべなおして、村正が言う。
「刀鍛冶でも習いましょうかねえ」
<<