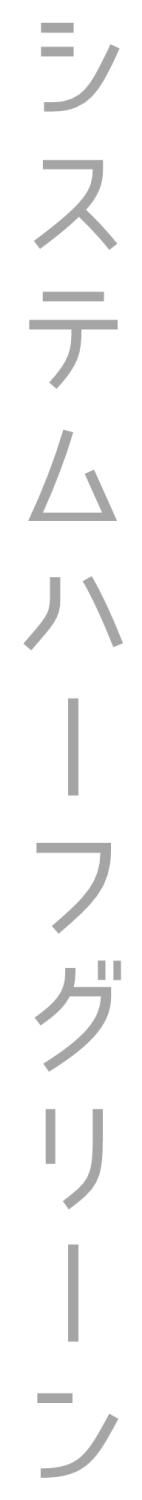
花は咲かないのか、というのがその時吹雪が口にし得た唯一の質問だった。後になって考えればもっと他に言うべきことがあったようにも思うのだが、あいにくその時にはこれ以外の言葉が出てこなかったのだ。
そしてひしぎは、残念ながら、と首をふったのだった。
「残念ながら、生殖は種子ではなく胞子です。したがって花は咲きません」
苔やぜんまいや海藻と同じですね、と彼は言う。
「胞子は専用の培養液に定着させないとすぐに死滅してしまうほど弱いですし、毒性もありません」
花が咲かないのはひしぎの言うとおり残念なことであるような気がした。もし咲くのなら毒々しい赤か、ささやかな白か、と吹雪は頭のどこか遠い部分で考えていた。
一時は相当危なかったらしいひしぎの、悪魔の眼移植後の経過は順調だった。無事に職場復帰を果たした彼はもうほとんど病の気配を感じさせない。左半身を覆うそれには少なからぬ奇異の視線が向けられていたが、太四老の位にあるひしぎに面と向かって理由を問う者はなかった。
「日常生活に不便はないのか」
「手入れはそれなりに必要です。彼らは生きていますから」
うす暗い研究室で吹雪に茶を淹れながら、「白黒の画面ではわからないと思いますが」とわけのわからない注釈をつけてひしぎは言った。
「悪魔の眼は、緑色をしています」
初耳だったが、話がどう繋がるのかわからない。手元の湯呑みの中の色を見ながら吹雪は問い返す。
「……それが?」
「衰えた私の体力を、悪魔の眼の持つエネルギーで補えると、以前説明しましたよね」
吹雪は頷く。その折のことはまだ記憶に新しい。
「なら、悪魔の眼はどうやってそのエネルギーを生み出していると思いますか」
エネルギー。
生み出す。
緑色。
「……ええ」
吹雪が正確な解答をはじき出したことを見て取って、ひしぎは低くゆっくりとそれを口にした。
「つまり、光合成です」
「…………花は、咲かないのか」
それが、己の半身に巣食うのは植物であると告げた彼に対して、その時吹雪が口にし得た唯一の質問だった。
ひしぎの言う「手入れ」はなかなかに面倒であるようだった。先日久々に吹雪と夕餉を共にしたひしぎの食物と水分の摂取量は大幅に増えていた。血管への寄生で養分を吸い取られる他に、皮膚表面への栄養剤の擦り込みも行っているらしい。
そして晴れた日には悪魔の眼を太陽にさらして光合成に励む必要がある。ここのところ雨が続いていたために、彼にとって今日は貴重な晴れ間であるはずだった。人払いした上での日光浴を終えた頃合いであろうひしぎを探して、さんさんと陽の注ぐ回廊の角を曲がる。
その吹雪の眼に、床でうつぶせに転がる黒衣の男。
駆け寄ってくる気配を感じたらしいひしぎが、重たげに頭を上げた。
「ひしぎ、お前」
「……吹雪……」
声がひどく掠れている。
「……水、を」
「飲むのか」
「かけてください……」
「量は」
「なんでも構いません、はやく……」
吹雪の指先がすみやかに渦巻く水を生み出し、ひしぎの上に浴びせかける。磨かれた床に光る水たまりを作ったそれは、じゅわ、と音を立てながら見てわかるほどの速さで彼の左半身に吸われていく。
ひしぎの中には確かに、苔やぜんまいや海藻と同じ類の、そしてそれらよりもはるかに獰猛なものが住んでいるのだ。
そして、そんな身体でも生きていてほしいと望んだのは。
やがて床を浸した水がほとんど消えたころ、彼らしからぬ緩慢な動作でひしぎがゆらりと濡れた身体を起こした。
「助かりました、吹雪」
「……気をつけて貰わねば困るな」
平静を保ちつつ吹雪は言った。
「蒸散が進みすぎて脱水症状を起こしたようです。以後注意します」
「葉はなくても蒸散はするのか」
「たいていの植物は葉以外の表皮からも水蒸気の排出を行いますよ」
それだけ言ってあとは何事もなかったかのように吹雪の用件を訊きはじめるひしぎの水に湿った肩からは、春の草に似た匂いがしていた。
その夜、夕陽が沈むのと同時にのぼった月が南の空にさしかかる時分に、吹雪の部屋の襖が音もなく開いた。
「……何の用だ」
「今夜が満月なので」
まったく答えになっていない答えを返してひしぎが吹雪の横をすり抜ける。旧くからの友人である彼が断りなしにやってくることは珍しくないが、こんな夜更けに現れることはまずなかった。いったい何事だ。吹雪は多少身構える。
「まあ、見ていてください」
ひしぎは他人の部屋の雨戸と障子を無遠慮に一枚分開け放し、そしておもむろに左腕を覆う黒いそれに手をかけた。この場にそぐわないその動作に不審の目を向ける吹雪の前で、普段はきつく巻かれて固定されている布が、中が見えない程度に緩められる。
途端。腕と布のすき間から、綿毛に似た白く軽い粒がまばらに溢れだした。ふわふわと漂うそれは風にのってあとからあとから暗い外へ流れていく。散りゆく花弁のような舞う粉雪のような粒子の流れが月光を浴びてうすい金色に輝くさまを、言葉もなく吹雪は見つめた。
ひしぎが淡々と口をひらく。
「悪魔の眼の生殖は種子ではなく胞子です。胞子は専用の培養液に定着させないとすぐに死滅してしまうほど弱いですし、毒性もありません」
いつかも聞いた説明だった。
「胞子は満月の晩にだけ放出されます。珊瑚の産卵のようなものです」
多少は趣があるでしょう、と言いながらひしぎは開け放した障子の外に顔を向ける。夜風が前髪を微かに揺らしている。
「……吹雪」
こちらを見ないままひしぎが低く呼んだ。数え切れぬほど呼ばれてきたはずのその響きを、吹雪は初めて耳にする特別な旋律のように聞く。
「現時点での感想ですが、」
この男は。
「そこまで、悪くなかったですよ。この身体も」
この男は、それを言いにきたのだ。
胞子を振りまきつづけるひしぎの腕。ひしぎに根を張りひしぎを生かす悪魔の眼。
頼りなく夜空に散っていく白い胞子の流れに吹雪は手を伸ばす。いくらか掴みとったはずのそれは、掌の中で溶けるように消えていった。
<<
そしてひしぎは、残念ながら、と首をふったのだった。
「残念ながら、生殖は種子ではなく胞子です。したがって花は咲きません」
苔やぜんまいや海藻と同じですね、と彼は言う。
「胞子は専用の培養液に定着させないとすぐに死滅してしまうほど弱いですし、毒性もありません」
花が咲かないのはひしぎの言うとおり残念なことであるような気がした。もし咲くのなら毒々しい赤か、ささやかな白か、と吹雪は頭のどこか遠い部分で考えていた。
一時は相当危なかったらしいひしぎの、悪魔の眼移植後の経過は順調だった。無事に職場復帰を果たした彼はもうほとんど病の気配を感じさせない。左半身を覆うそれには少なからぬ奇異の視線が向けられていたが、太四老の位にあるひしぎに面と向かって理由を問う者はなかった。
「日常生活に不便はないのか」
「手入れはそれなりに必要です。彼らは生きていますから」
うす暗い研究室で吹雪に茶を淹れながら、「白黒の画面ではわからないと思いますが」とわけのわからない注釈をつけてひしぎは言った。
「悪魔の眼は、緑色をしています」
初耳だったが、話がどう繋がるのかわからない。手元の湯呑みの中の色を見ながら吹雪は問い返す。
「……それが?」
「衰えた私の体力を、悪魔の眼の持つエネルギーで補えると、以前説明しましたよね」
吹雪は頷く。その折のことはまだ記憶に新しい。
「なら、悪魔の眼はどうやってそのエネルギーを生み出していると思いますか」
エネルギー。
生み出す。
緑色。
「……ええ」
吹雪が正確な解答をはじき出したことを見て取って、ひしぎは低くゆっくりとそれを口にした。
「つまり、光合成です」
「…………花は、咲かないのか」
それが、己の半身に巣食うのは植物であると告げた彼に対して、その時吹雪が口にし得た唯一の質問だった。
ひしぎの言う「手入れ」はなかなかに面倒であるようだった。先日久々に吹雪と夕餉を共にしたひしぎの食物と水分の摂取量は大幅に増えていた。血管への寄生で養分を吸い取られる他に、皮膚表面への栄養剤の擦り込みも行っているらしい。
そして晴れた日には悪魔の眼を太陽にさらして光合成に励む必要がある。ここのところ雨が続いていたために、彼にとって今日は貴重な晴れ間であるはずだった。人払いした上での日光浴を終えた頃合いであろうひしぎを探して、さんさんと陽の注ぐ回廊の角を曲がる。
その吹雪の眼に、床でうつぶせに転がる黒衣の男。
駆け寄ってくる気配を感じたらしいひしぎが、重たげに頭を上げた。
「ひしぎ、お前」
「……吹雪……」
声がひどく掠れている。
「……水、を」
「飲むのか」
「かけてください……」
「量は」
「なんでも構いません、はやく……」
吹雪の指先がすみやかに渦巻く水を生み出し、ひしぎの上に浴びせかける。磨かれた床に光る水たまりを作ったそれは、じゅわ、と音を立てながら見てわかるほどの速さで彼の左半身に吸われていく。
ひしぎの中には確かに、苔やぜんまいや海藻と同じ類の、そしてそれらよりもはるかに獰猛なものが住んでいるのだ。
そして、そんな身体でも生きていてほしいと望んだのは。
やがて床を浸した水がほとんど消えたころ、彼らしからぬ緩慢な動作でひしぎがゆらりと濡れた身体を起こした。
「助かりました、吹雪」
「……気をつけて貰わねば困るな」
平静を保ちつつ吹雪は言った。
「蒸散が進みすぎて脱水症状を起こしたようです。以後注意します」
「葉はなくても蒸散はするのか」
「たいていの植物は葉以外の表皮からも水蒸気の排出を行いますよ」
それだけ言ってあとは何事もなかったかのように吹雪の用件を訊きはじめるひしぎの水に湿った肩からは、春の草に似た匂いがしていた。
その夜、夕陽が沈むのと同時にのぼった月が南の空にさしかかる時分に、吹雪の部屋の襖が音もなく開いた。
「……何の用だ」
「今夜が満月なので」
まったく答えになっていない答えを返してひしぎが吹雪の横をすり抜ける。旧くからの友人である彼が断りなしにやってくることは珍しくないが、こんな夜更けに現れることはまずなかった。いったい何事だ。吹雪は多少身構える。
「まあ、見ていてください」
ひしぎは他人の部屋の雨戸と障子を無遠慮に一枚分開け放し、そしておもむろに左腕を覆う黒いそれに手をかけた。この場にそぐわないその動作に不審の目を向ける吹雪の前で、普段はきつく巻かれて固定されている布が、中が見えない程度に緩められる。
途端。腕と布のすき間から、綿毛に似た白く軽い粒がまばらに溢れだした。ふわふわと漂うそれは風にのってあとからあとから暗い外へ流れていく。散りゆく花弁のような舞う粉雪のような粒子の流れが月光を浴びてうすい金色に輝くさまを、言葉もなく吹雪は見つめた。
ひしぎが淡々と口をひらく。
「悪魔の眼の生殖は種子ではなく胞子です。胞子は専用の培養液に定着させないとすぐに死滅してしまうほど弱いですし、毒性もありません」
いつかも聞いた説明だった。
「胞子は満月の晩にだけ放出されます。珊瑚の産卵のようなものです」
多少は趣があるでしょう、と言いながらひしぎは開け放した障子の外に顔を向ける。夜風が前髪を微かに揺らしている。
「……吹雪」
こちらを見ないままひしぎが低く呼んだ。数え切れぬほど呼ばれてきたはずのその響きを、吹雪は初めて耳にする特別な旋律のように聞く。
「現時点での感想ですが、」
この男は。
「そこまで、悪くなかったですよ。この身体も」
この男は、それを言いにきたのだ。
胞子を振りまきつづけるひしぎの腕。ひしぎに根を張りひしぎを生かす悪魔の眼。
頼りなく夜空に散っていく白い胞子の流れに吹雪は手を伸ばす。いくらか掴みとったはずのそれは、掌の中で溶けるように消えていった。
<<