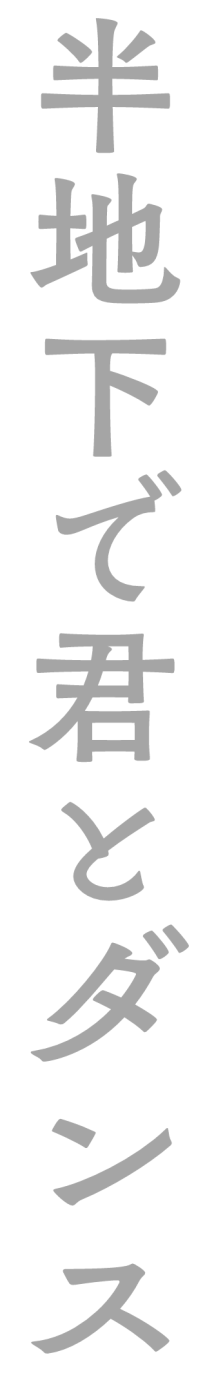
この時、この場所でだけだ。
吹雪の額が汗ばむのも、ひしぎの息が熱くなるのも。
「吹雪」
誘うのはいつも自分からで、ひしぎはそれを少しだけ不満に思っている。
「……今夜あたり、どうです」
まだ真っ昼間、執務中である。彼の耳元に小さく囁くと、吹雪は若干考えるような様子を見せてから、いいだろう、と応えた。それだけで心身が柄にもなく高揚してくるのをひしぎは感じる。ここのところご無沙汰だったせいだろうか。
「前回はなしでしたが、今度はなにか使いますか」
一応それも訊いておく。趣向は毎回変えているのだ。
「……短めにするか」
「なら、このくらいで」
ひしぎが両手で、てのひら一つ分ほどの長さを示す。
「そういえば、あのときの傷はどうした」
「傷?」
「背中のだ」
「ああ」
先日の夜、吹雪の爪がひしぎの背につけたものだった。もともとたいした出血ではなかったし、痕も残っていない。ひしぎがそれを告げると、そうか、と言う。彼なりに気にしていたらしい。
「けれど今回はそれもなしでお願いします」
「水龍はどうする」
「それも、なしで」
あれを使われると少々きついのだ。
吹雪が眼で頷く。これ以上の確認は必要ない。いつもの時間、いつもの場所。そこで彼が、待っている。
一人ではできることに限界がある。こういう行為はやはり誰かとするのが一番で、しかし太四老ともなるとだいぶ相手が限られてくる。気兼ねなく一戦交えられるのは、今ではもうお互いだけだった。
前回は少し激しすぎたかもしれないとひしぎは反省する。終わった後は双方それなりに消耗するためそう頻繁にするわけにもいかない。多いときでも三日おき程度。その三日が、ひしぎにはひどくもどかしい。
暗い石段を下りていく。
紅の塔上層部から直接つながるこの部屋の存在を知るものは少ない。半分地下に埋めこまれる形になっていて、物音が洩れないよう工夫されている。中で何が行われていようと外部にはわからない。
扉の前に立ち、重いそれをひしぎはゆっくり押し開く。
厚い石壁で囲まれた円い部屋の中央に、こちらに背を向けて吹雪が立っていた。その手には純白の扇。単なる木と紙でできているはずのそれが、彼にかかれば桁外れの殺傷能力を持つようになることをひしぎはよく知っている。
対するひしぎの右手には漆塗りの箸一本。今回は得物あり、短め、という事前の打ち合わせ通りだ。吹雪の爪は使用不可。水龍も不可。お互い武器はこれだけ。相手に大きな傷を負わせないようにしかしできる限り本気で、というのが二人の手合わせの取り決めだった。太四老といえども、常日頃の鍛錬を怠るわけにはいかないのである。
多くて三日おき。
この時、この場所でだけだ。吹雪の額が汗ばむのも、ひしぎの息が熱くなるのも。
吹雪がゆっくりと振り返った。途端に重さを増した殺気がひしぎの全身を心地よく打つ。流れるような動作で吹雪が構える。扇が優雅な曲線を描いて、ひしぎの奥底に息づくひとつの感情が勝手に躍りはじめる。
これは紛れもない歓喜だ。相手のもつ美しくも恐るべき技量への。これから始まる密かで熾烈な攻防への。
扇の先を鋭くひしぎに向けて、吹雪が開始を宣言する。
「……来い」
言われなくとも。
<<
吹雪の額が汗ばむのも、ひしぎの息が熱くなるのも。
「吹雪」
誘うのはいつも自分からで、ひしぎはそれを少しだけ不満に思っている。
「……今夜あたり、どうです」
まだ真っ昼間、執務中である。彼の耳元に小さく囁くと、吹雪は若干考えるような様子を見せてから、いいだろう、と応えた。それだけで心身が柄にもなく高揚してくるのをひしぎは感じる。ここのところご無沙汰だったせいだろうか。
「前回はなしでしたが、今度はなにか使いますか」
一応それも訊いておく。趣向は毎回変えているのだ。
「……短めにするか」
「なら、このくらいで」
ひしぎが両手で、てのひら一つ分ほどの長さを示す。
「そういえば、あのときの傷はどうした」
「傷?」
「背中のだ」
「ああ」
先日の夜、吹雪の爪がひしぎの背につけたものだった。もともとたいした出血ではなかったし、痕も残っていない。ひしぎがそれを告げると、そうか、と言う。彼なりに気にしていたらしい。
「けれど今回はそれもなしでお願いします」
「水龍はどうする」
「それも、なしで」
あれを使われると少々きついのだ。
吹雪が眼で頷く。これ以上の確認は必要ない。いつもの時間、いつもの場所。そこで彼が、待っている。
一人ではできることに限界がある。こういう行為はやはり誰かとするのが一番で、しかし太四老ともなるとだいぶ相手が限られてくる。気兼ねなく一戦交えられるのは、今ではもうお互いだけだった。
前回は少し激しすぎたかもしれないとひしぎは反省する。終わった後は双方それなりに消耗するためそう頻繁にするわけにもいかない。多いときでも三日おき程度。その三日が、ひしぎにはひどくもどかしい。
暗い石段を下りていく。
紅の塔上層部から直接つながるこの部屋の存在を知るものは少ない。半分地下に埋めこまれる形になっていて、物音が洩れないよう工夫されている。中で何が行われていようと外部にはわからない。
扉の前に立ち、重いそれをひしぎはゆっくり押し開く。
厚い石壁で囲まれた円い部屋の中央に、こちらに背を向けて吹雪が立っていた。その手には純白の扇。単なる木と紙でできているはずのそれが、彼にかかれば桁外れの殺傷能力を持つようになることをひしぎはよく知っている。
対するひしぎの右手には漆塗りの箸一本。今回は得物あり、短め、という事前の打ち合わせ通りだ。吹雪の爪は使用不可。水龍も不可。お互い武器はこれだけ。相手に大きな傷を負わせないようにしかしできる限り本気で、というのが二人の手合わせの取り決めだった。太四老といえども、常日頃の鍛錬を怠るわけにはいかないのである。
多くて三日おき。
この時、この場所でだけだ。吹雪の額が汗ばむのも、ひしぎの息が熱くなるのも。
吹雪がゆっくりと振り返った。途端に重さを増した殺気がひしぎの全身を心地よく打つ。流れるような動作で吹雪が構える。扇が優雅な曲線を描いて、ひしぎの奥底に息づくひとつの感情が勝手に躍りはじめる。
これは紛れもない歓喜だ。相手のもつ美しくも恐るべき技量への。これから始まる密かで熾烈な攻防への。
扇の先を鋭くひしぎに向けて、吹雪が開始を宣言する。
「……来い」
言われなくとも。
<<