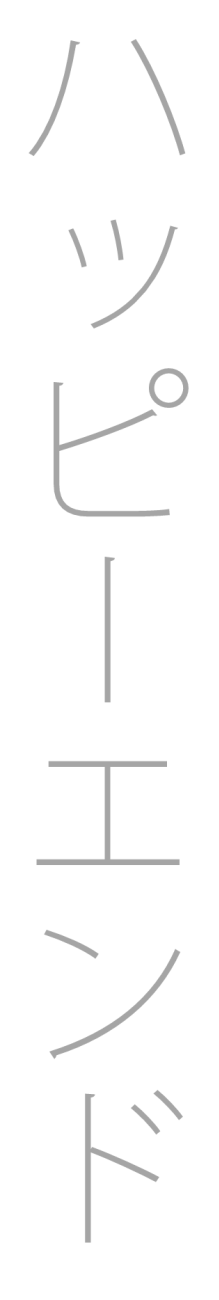
こんな夢を見た。
私は視点だけの存在になっていた。身体はない。意識だけがはっきりとあって、ふわふわと世界を見ている。ここでの私はもう死んでいるのかもしれない。曖昧に揺らぐ景色の中、視点だけになった私は自分の研究室の壁を泳ぐようにすりぬけて、紅の塔の廊下に出る。
塔はまったくの無人だった。誰もいない。誰もいない。不穏なほどの静寂。
吹雪。
とっさにその名前が思い浮かんで、私は友人の姿を探した。
ここはもう私のほかに誰ひとり存在していないと、なぜだかそう悟った。陰陽殿の扉をするりと越え、身体のない私は彼を探して外へ出ていく。
外は重い曇り空だった。雪のような灰のような白いものがちらちらと舞っている。
城下町を貫く大通りの中央に、吹雪はいた。すぐ後ろに漂っている視点だけの私には気づかない。上空から絶え間なく、はかなく細かい粒子がさらに密度を増してそそいでいる。天を見上げて立つ吹雪の後ろ姿にもそれは降りかかる。静かにそして圧倒的な量で一面に降る白、私はこれが何なのかを知っている。
砂だ。
かりそめの命の、燃えつきた証だ。
生きているものの気配はこの街のどこにもなかった。誰もいない。誰もいない。ただ砂だけが降っている。みんないってしまった、みんないなくなってしまった、みんな死んでしまった。私を含めて。ひとり残らず。彼だけを置きざりにして。
白い砂があとからあとから無人の街に舞い下りてくる。やさしく私の視界を覆う。最悪の結末、この世でもっとも見たくない光景のはずなのに、私はぼんやりと場違いな感想を抱いていた。きれいだ。
いくら降っても砂は積もらなかった。石畳の上をしばらく渦巻いてあっけなく消えてしまう。何も悲しむことはない、無から作りだされたものが元の無にかえるだけなのだ、と頭のどこかが考える。その一方で別のどこかが、誰かがたとえば吹雪が悲しむならば、それはまぎれもなく悲しいことなのだ、と考える。
吹雪の背中は泣いているようだった。
立ちつくすその肩を抱きたいような思いがふいにこみあげる。
けれどそれはできなかった。
視点だけの存在になってしまった私には、腕がなかった。
彼と一緒に泣きたかったけれど、眼が、なかった。
夢からさめると薄暗い明け方で、私は部屋にひとつしかない小さな窓を開けて空を確かめる。星がまだいくつか残っている。砂など降りそうにない晴天。
あんな結末は許さない。あんな終わりには絶対にさせない。大丈夫、私にはまだ、そのために使える両腕がある。
泣くには早い。
<<
私は視点だけの存在になっていた。身体はない。意識だけがはっきりとあって、ふわふわと世界を見ている。ここでの私はもう死んでいるのかもしれない。曖昧に揺らぐ景色の中、視点だけになった私は自分の研究室の壁を泳ぐようにすりぬけて、紅の塔の廊下に出る。
塔はまったくの無人だった。誰もいない。誰もいない。不穏なほどの静寂。
吹雪。
とっさにその名前が思い浮かんで、私は友人の姿を探した。
ここはもう私のほかに誰ひとり存在していないと、なぜだかそう悟った。陰陽殿の扉をするりと越え、身体のない私は彼を探して外へ出ていく。
外は重い曇り空だった。雪のような灰のような白いものがちらちらと舞っている。
城下町を貫く大通りの中央に、吹雪はいた。すぐ後ろに漂っている視点だけの私には気づかない。上空から絶え間なく、はかなく細かい粒子がさらに密度を増してそそいでいる。天を見上げて立つ吹雪の後ろ姿にもそれは降りかかる。静かにそして圧倒的な量で一面に降る白、私はこれが何なのかを知っている。
砂だ。
かりそめの命の、燃えつきた証だ。
生きているものの気配はこの街のどこにもなかった。誰もいない。誰もいない。ただ砂だけが降っている。みんないってしまった、みんないなくなってしまった、みんな死んでしまった。私を含めて。ひとり残らず。彼だけを置きざりにして。
白い砂があとからあとから無人の街に舞い下りてくる。やさしく私の視界を覆う。最悪の結末、この世でもっとも見たくない光景のはずなのに、私はぼんやりと場違いな感想を抱いていた。きれいだ。
いくら降っても砂は積もらなかった。石畳の上をしばらく渦巻いてあっけなく消えてしまう。何も悲しむことはない、無から作りだされたものが元の無にかえるだけなのだ、と頭のどこかが考える。その一方で別のどこかが、誰かがたとえば吹雪が悲しむならば、それはまぎれもなく悲しいことなのだ、と考える。
吹雪の背中は泣いているようだった。
立ちつくすその肩を抱きたいような思いがふいにこみあげる。
けれどそれはできなかった。
視点だけの存在になってしまった私には、腕がなかった。
彼と一緒に泣きたかったけれど、眼が、なかった。
夢からさめると薄暗い明け方で、私は部屋にひとつしかない小さな窓を開けて空を確かめる。星がまだいくつか残っている。砂など降りそうにない晴天。
あんな結末は許さない。あんな終わりには絶対にさせない。大丈夫、私にはまだ、そのために使える両腕がある。
泣くには早い。
<<