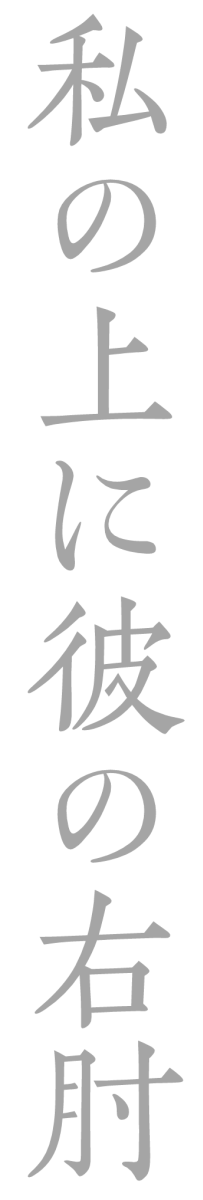
私は彼の所有物である。
私の主であるところの彼の名を吹雪という。一族の最高幹部たる太四老の長、その地位にふさわしい圧倒的な実力と風格とを備えた、無明歳刑流を極めし水の使い手である。
陰陽殿の彼の居城、広いその一室で。彼は私をいつも傍に置き、畳に横たわる私の上に右腕をのせる。時折その手で私の背を撫でることもある。彼に所有され、用いられ、こうしてかたわらに在れることは、私の誇りであり至上の幸福である。彼の手に触れられるがまま、私は常に黙ってじっとしている。私の背の、彼のてのひらの感触。彼の腕の重み。私は動かない。何も言わない。
より正確に表現するならば。
私は動かないのではない。動かないのではなく、己の力で動くことが私にはできない。何も言わないのではなく、声を発するという行為が私にはできない。
私は人のかたちをしていない。
私は彼の脇息である。
名前はまだ、ない。
主の肘置きとしての機能しか持たない私だが、肘置きである私にのみ語り得ることというのも確かに存在する。今日は私の主こと吹雪と、その友人である黒衣の男について話してみたい。
この男、名をひしぎという。優れた研究者であり、同時に主と同じく太四老の名を戴く一人であり、その腕は歴代最強とも称されていると聞く。
さて、主とこのひしぎとが、いかなる経緯をもって友と呼べる間柄になったのかを私は知らない。一般に、器物が自我を持つまでにはおよそ百年弱の月日が必要とされている。私が文字通りものごころついた時分には、彼らふたりはすでに現在とほぼ変わらぬ形をなしていたのである。
「……その件については、実はわたしもよく知らないのだ」
そう言っていたのは白夜。武骨な漆黒の柄と、闇に煌めく幅広の片刃をもつ、ひしぎ愛用の得物である。刀である白夜と脇息である私が顔を合わせる機会はそう多くはなかったが、ひしぎが帯刀して主の部屋にあらわれる際には声なき声でよく言葉をかわしあった。
「わたしの生まれる前からの付き合いであることは解る。……逆に言うならば、それしか解らない」
簡潔に言ってからひと息置いて、「そもそも」と相手は言葉を継ぐ。
「わたしの主とおまえの主が友人であるという前提は、はたして正しいのか?」
所有者の思考に馴染んでか、それとも元々そういう風に作られたのか、白夜は若干理屈っぽい性質であった。
「主らをよく知らぬ者からは、そうは見えぬらしいが」
私はそれに同意する。彼ら二人の仲は、良好な関係の友人と受け取るのが難しい程度には冷ややかで、単なる同僚で片づけるには奇妙に濃密だ。周囲にはさぞ不可解に映っているだろう。
「主がわたしを握るとき、主の思考のどこかにはいつもおまえの主の名がある」
刀とその優れた使用者の間では、サトリの能力がなくとも意志の疎通が可能である。白夜とひしぎもその例に洩れない。
暗がりを探るような慎重さで、白夜は呟く。
「……友とは、そのようなものなのだろうか」
わからない、と私は答えた。
「あれが知らぬのも無理もない。あれが作られたのは、我よりも少々後のことだ」
白夜についてそう述べたのは、私の主である吹雪の愛刀。すらりと十字に伸びた鍔の装飾が、主に似て鋭利な印象を与える一振りである。
武器として生まれたものならば、己を所有する存在と心を通わせ会話することができる。その点において私は主の刀を心底羨んでいた。私と主が触れ合うのは会話によってではなく、ただ私の上に置かれる主の右腕によってのみであったからだ。
けれど一方で主の刀は、同じ刀剣の身でありながらも持ち主から固有の名を賜っている白夜を羨んでいるのだった。主の刀が白夜をその名で呼ばず、『あれ』で済ませているのはそういった理由である。
「しかし、我に意識が生じた時にも既に、主の側には村正やひしぎの姿があったと記憶している。我らの主と彼らが知り合うたのは、おそらくそれよりずっと以前なのであろう」
では、主からひしぎとの過去についての話を聞いたことはないだろうか。
「無いな」
相手は即答する。
「主は我に昔のことを語らない。我にはただ、主が我を振るう一瞬と、その先に開ける道だけがある」
その瞬間を思い出してか、夢見るような口調で主の刀は言う。同じ高揚を私も知っている。私たちは主の道具で、主のために使われることは無上の喜びだ。
しかし、ひしぎはどうなのだろう。道具として生まれなかった、人のかたちをしているひしぎは。
「ひとつ訊きたいのだが……」
こちらの呈した質問は、逆に質問で返された。
「何ゆえ貴殿が、あの男のことをそこまで気にかける」
私は少し考えて、わからない、と答えた。ふむ、と主の刀もしばし黙りこむ。
「……我は、ひしぎを斬ったことがある」
初めて聞く話だった。もし眼があったなら瞠目していただろう私に、相手は「掠った程度だがな」とその先をつづける。
どういった経緯でその事件が起きたのかについて、主の刀はそれ以上触れなかった。ただそれまでより少し柔らかに、私にこう問いかけた。
「貴殿にもあるのだろう? 貴殿しか知らぬ出来事が。……我に、刀である我にしか知り得ぬことがあったように」
そうだ。
私にもあったのだった。
脇息である私だからこそ知り得た出来事が。
私の中に刻まれた、ひとつの光景が。
その日もひしぎがこの一室を訪れていた。何についての会話だったか、聞くともなしに私はそれを聞いていた。主は私の背にもたれ、相対してひしぎが立つ。主とひしぎの他には誰ひとりとして聞く者のないやりとりだが、双方の声に親しげな響きはまるでない。主の表情は険しく、ひしぎの言葉には棘がある。
ひしぎは挑発し、抉り、咎める。
主は突き放し、遮り、退ける。
けれど私は知っていた。この場所から長いあいだ、こうして彼らを眺めてきた私は知っていた。主がひしぎの背に、ひしぎが主の後ろ肩に、ひそかに投げかける気遣わしげな視線のことを。ほんの時々かわされる、穏やかな会話の切れ端のことを。それらに含まれるごく微かな温みの気配を。
そしてこの時、またひとつ私は知る。
この身をもって、知ることになる。
まだ何か言いたげな相手を残して主は席を立った。ひしぎは主が部屋を去ったあともしばらくその場に立ちつくしていた。主の存在を失くした空間に、水底のような静寂が満ちる。
やがて。
影にも似た長身がゆらりと動いた。
主の座していた一段高い畳に、ひしぎが音もなく膝を折る。
唐突なその所作を私が不審に思う間に。
彼の片腕が、すっと伸びてくる。
その手が、私に。
たった今まで主が肘を置いていた私の背に、触れる。
私は少なからぬ動揺を覚えた。脇息である私の皮膚、薄くなめらかな絹張りのその上に、ごく軽くのせられた、主ではない感触。素肌の右手。少し冷えた指先。額から滑り落ちる彼の前髪、その向こうで伏せられた瞼。
それは祈りのようだった。
私の前で膝をつき俯いていたひしぎが、静かに立ち上がり身を翻すまでを、私はもどかしいような呆れたような思いで見守っていた。ひしぎは手も口も持たない私とは違う。己の力で動くことができず、主に言葉を伝えることもできない私とは違う。手があるならその手でできることをすればいいし、口があるならその口で言いたいことを言えばいいのだ。
優しくしたいのなら、優しくすればよかったのだ。
しかしどうやらひしぎはそれをしなかった。できなかったのかもしれないし、最初からそのつもりはなかったのかもしれない。それを判断する術は私にはない。彼が何を考えていたのかはもう誰にもわからない。ただ、私の個人的な――個物的な見解を述べさせてもらうならば。
ひしぎが主に向けるあの眼差しは、主が主のひとり娘を見守るときのそれに、確かによく似ていた。
崩れた塔の跡から運よく見つけ出された私は、主の娘に引き取られ、いま彼女の庇護下にて余生をすごしている。
彼女は私を脇息として用いず、帰郷の折に眺めたりそっと触れたりするだけであるが、私は今なお紛れもなく脇息である。名前はまだなくこれからもない。主が私の上に肘を置くことはもう二度とない。しかし私は今でも、そして永遠に、彼の所有物である。
<<
私の主であるところの彼の名を吹雪という。一族の最高幹部たる太四老の長、その地位にふさわしい圧倒的な実力と風格とを備えた、無明歳刑流を極めし水の使い手である。
陰陽殿の彼の居城、広いその一室で。彼は私をいつも傍に置き、畳に横たわる私の上に右腕をのせる。時折その手で私の背を撫でることもある。彼に所有され、用いられ、こうしてかたわらに在れることは、私の誇りであり至上の幸福である。彼の手に触れられるがまま、私は常に黙ってじっとしている。私の背の、彼のてのひらの感触。彼の腕の重み。私は動かない。何も言わない。
より正確に表現するならば。
私は動かないのではない。動かないのではなく、己の力で動くことが私にはできない。何も言わないのではなく、声を発するという行為が私にはできない。
私は人のかたちをしていない。
私は彼の脇息である。
名前はまだ、ない。
主の肘置きとしての機能しか持たない私だが、肘置きである私にのみ語り得ることというのも確かに存在する。今日は私の主こと吹雪と、その友人である黒衣の男について話してみたい。
この男、名をひしぎという。優れた研究者であり、同時に主と同じく太四老の名を戴く一人であり、その腕は歴代最強とも称されていると聞く。
さて、主とこのひしぎとが、いかなる経緯をもって友と呼べる間柄になったのかを私は知らない。一般に、器物が自我を持つまでにはおよそ百年弱の月日が必要とされている。私が文字通りものごころついた時分には、彼らふたりはすでに現在とほぼ変わらぬ形をなしていたのである。
「……その件については、実はわたしもよく知らないのだ」
そう言っていたのは白夜。武骨な漆黒の柄と、闇に煌めく幅広の片刃をもつ、ひしぎ愛用の得物である。刀である白夜と脇息である私が顔を合わせる機会はそう多くはなかったが、ひしぎが帯刀して主の部屋にあらわれる際には声なき声でよく言葉をかわしあった。
「わたしの生まれる前からの付き合いであることは解る。……逆に言うならば、それしか解らない」
簡潔に言ってからひと息置いて、「そもそも」と相手は言葉を継ぐ。
「わたしの主とおまえの主が友人であるという前提は、はたして正しいのか?」
所有者の思考に馴染んでか、それとも元々そういう風に作られたのか、白夜は若干理屈っぽい性質であった。
「主らをよく知らぬ者からは、そうは見えぬらしいが」
私はそれに同意する。彼ら二人の仲は、良好な関係の友人と受け取るのが難しい程度には冷ややかで、単なる同僚で片づけるには奇妙に濃密だ。周囲にはさぞ不可解に映っているだろう。
「主がわたしを握るとき、主の思考のどこかにはいつもおまえの主の名がある」
刀とその優れた使用者の間では、サトリの能力がなくとも意志の疎通が可能である。白夜とひしぎもその例に洩れない。
暗がりを探るような慎重さで、白夜は呟く。
「……友とは、そのようなものなのだろうか」
わからない、と私は答えた。
「あれが知らぬのも無理もない。あれが作られたのは、我よりも少々後のことだ」
白夜についてそう述べたのは、私の主である吹雪の愛刀。すらりと十字に伸びた鍔の装飾が、主に似て鋭利な印象を与える一振りである。
武器として生まれたものならば、己を所有する存在と心を通わせ会話することができる。その点において私は主の刀を心底羨んでいた。私と主が触れ合うのは会話によってではなく、ただ私の上に置かれる主の右腕によってのみであったからだ。
けれど一方で主の刀は、同じ刀剣の身でありながらも持ち主から固有の名を賜っている白夜を羨んでいるのだった。主の刀が白夜をその名で呼ばず、『あれ』で済ませているのはそういった理由である。
「しかし、我に意識が生じた時にも既に、主の側には村正やひしぎの姿があったと記憶している。我らの主と彼らが知り合うたのは、おそらくそれよりずっと以前なのであろう」
では、主からひしぎとの過去についての話を聞いたことはないだろうか。
「無いな」
相手は即答する。
「主は我に昔のことを語らない。我にはただ、主が我を振るう一瞬と、その先に開ける道だけがある」
その瞬間を思い出してか、夢見るような口調で主の刀は言う。同じ高揚を私も知っている。私たちは主の道具で、主のために使われることは無上の喜びだ。
しかし、ひしぎはどうなのだろう。道具として生まれなかった、人のかたちをしているひしぎは。
「ひとつ訊きたいのだが……」
こちらの呈した質問は、逆に質問で返された。
「何ゆえ貴殿が、あの男のことをそこまで気にかける」
私は少し考えて、わからない、と答えた。ふむ、と主の刀もしばし黙りこむ。
「……我は、ひしぎを斬ったことがある」
初めて聞く話だった。もし眼があったなら瞠目していただろう私に、相手は「掠った程度だがな」とその先をつづける。
どういった経緯でその事件が起きたのかについて、主の刀はそれ以上触れなかった。ただそれまでより少し柔らかに、私にこう問いかけた。
「貴殿にもあるのだろう? 貴殿しか知らぬ出来事が。……我に、刀である我にしか知り得ぬことがあったように」
そうだ。
私にもあったのだった。
脇息である私だからこそ知り得た出来事が。
私の中に刻まれた、ひとつの光景が。
その日もひしぎがこの一室を訪れていた。何についての会話だったか、聞くともなしに私はそれを聞いていた。主は私の背にもたれ、相対してひしぎが立つ。主とひしぎの他には誰ひとりとして聞く者のないやりとりだが、双方の声に親しげな響きはまるでない。主の表情は険しく、ひしぎの言葉には棘がある。
ひしぎは挑発し、抉り、咎める。
主は突き放し、遮り、退ける。
けれど私は知っていた。この場所から長いあいだ、こうして彼らを眺めてきた私は知っていた。主がひしぎの背に、ひしぎが主の後ろ肩に、ひそかに投げかける気遣わしげな視線のことを。ほんの時々かわされる、穏やかな会話の切れ端のことを。それらに含まれるごく微かな温みの気配を。
そしてこの時、またひとつ私は知る。
この身をもって、知ることになる。
まだ何か言いたげな相手を残して主は席を立った。ひしぎは主が部屋を去ったあともしばらくその場に立ちつくしていた。主の存在を失くした空間に、水底のような静寂が満ちる。
やがて。
影にも似た長身がゆらりと動いた。
主の座していた一段高い畳に、ひしぎが音もなく膝を折る。
唐突なその所作を私が不審に思う間に。
彼の片腕が、すっと伸びてくる。
その手が、私に。
たった今まで主が肘を置いていた私の背に、触れる。
私は少なからぬ動揺を覚えた。脇息である私の皮膚、薄くなめらかな絹張りのその上に、ごく軽くのせられた、主ではない感触。素肌の右手。少し冷えた指先。額から滑り落ちる彼の前髪、その向こうで伏せられた瞼。
それは祈りのようだった。
私の前で膝をつき俯いていたひしぎが、静かに立ち上がり身を翻すまでを、私はもどかしいような呆れたような思いで見守っていた。ひしぎは手も口も持たない私とは違う。己の力で動くことができず、主に言葉を伝えることもできない私とは違う。手があるならその手でできることをすればいいし、口があるならその口で言いたいことを言えばいいのだ。
優しくしたいのなら、優しくすればよかったのだ。
しかしどうやらひしぎはそれをしなかった。できなかったのかもしれないし、最初からそのつもりはなかったのかもしれない。それを判断する術は私にはない。彼が何を考えていたのかはもう誰にもわからない。ただ、私の個人的な――個物的な見解を述べさせてもらうならば。
ひしぎが主に向けるあの眼差しは、主が主のひとり娘を見守るときのそれに、確かによく似ていた。
崩れた塔の跡から運よく見つけ出された私は、主の娘に引き取られ、いま彼女の庇護下にて余生をすごしている。
彼女は私を脇息として用いず、帰郷の折に眺めたりそっと触れたりするだけであるが、私は今なお紛れもなく脇息である。名前はまだなくこれからもない。主が私の上に肘を置くことはもう二度とない。しかし私は今でも、そして永遠に、彼の所有物である。
<<