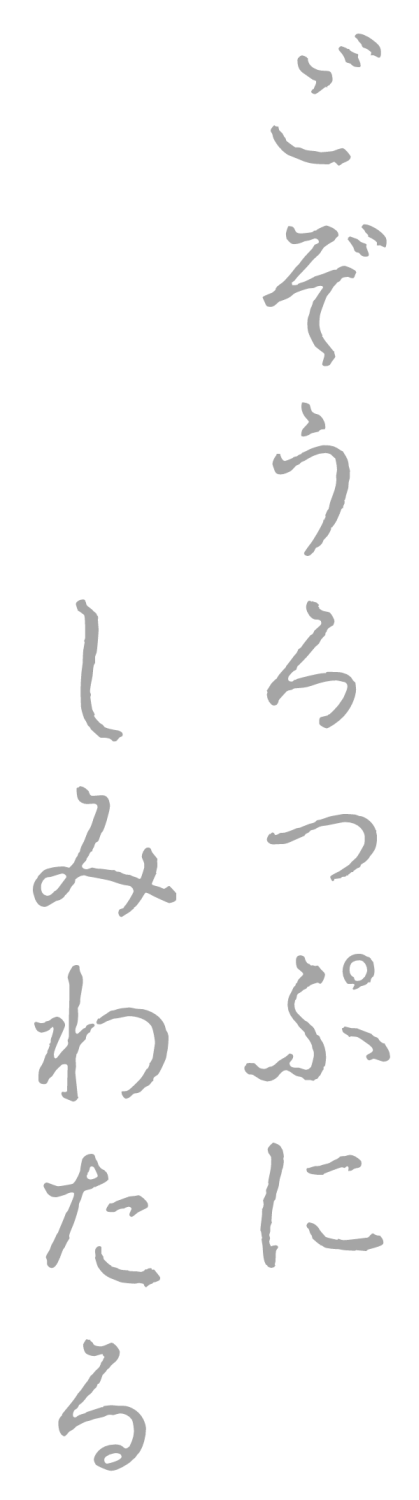
処分しました、とひしぎは答えた。
子供の手習いに良さそうな本はあるか、との吹雪の問いである。あらゆる種類の蔵書をためこんでいた彼の書庫ならば大抵のものはそろっているだろう、それも子供向けの本ならば特に充実していてもおかしくない、と踏んでいた吹雪の予測はおおいに外れた。
背を向けたまま手元に視線を落とし、吹雪には用途の見当もつかない器具を扱いながらひしぎは言う。
「もう随分前に、研究に必要な分を残してほとんど整理してしまいましたので……」
直射日光が入らないように塞がれた窓をちらりと見遣って、吹雪は重ねて何故だと問う。かつてはそれなりに快適な住環境であったはずのひしぎの居城は、いつからかすっかり様変わりしていた。所狭しと資料が積まれ、標本が林立し、昼だというのにあたりは薄暗い。
「必要がないからです」
無感情に、平坦な声が返る。
「私には、もう必要のないものですから。……辰伶用でしたか? それとも時人の? 申し訳ないですが、他をあたってもらえませんか」
――いつからだ。この男がこうなったのは。
真っ先に思いつく心当たりはひとつある。あれ以降、ひしぎは何かにつけて繰り返すようになった。
あの日私は誓いましたから。私はあなたに。どこまでも。地獄の底まで。
ひしぎが執拗に口に出すそのたびに、吹雪の喉元に居心地の悪さが粘りつく。
「……気に入らんな」
「何がです」
「お前のそういう姿勢がだ」
「本当に?」
作業の手をとめたひしぎが振り向いた。
「本当は、歓迎しているのではないですか?」
「……何をだ」
「私の、こういう姿勢を」
――いつから。いつからだっただろう。以前からその兆候は存在していた。姫時が逝ってから。一族の真実を知ってから。村正が去ってから。または彼自身が病を得たころから。そしてあの日、誓いを口にしてから。
ひしぎが変わってゆく。ただひとつの重要なもののためだけに、その精神から余計なものが削ぎ落とされ研ぎ澄まされる。濾過され蒸留され、ひとつの意志だけが純度を増してゆく。
何のために。
その答えを吹雪は知っている。今の彼にとってただひとつ重要なそれが、何なのかを知っている。
「私が、」
それが何なのか。
その答えを、かつてなく直接的に、ひしぎが唇にのせる。
「私があなたの望みのために生きているというのは、どんな気分ですか……?」
ひしぎはどんなことでもやってのけるだろう。吹雪の欲する未来のためなら。
「どんな気分ですか、吹雪」
時に過剰なほどのその献身は、実際問題としてありがたく心強く、その一方で不可解であり苛立たしくもあり、そしてそれは。
「……悪くないと、思っているのでは?」
それはうっすらと、後ろ暗い快さを含んでいる。
吹雪の優先順位の頂点は決してひしぎにはなり得ないのに、ひしぎのその位置には常に吹雪がいるということ。己の望みのために力を尽くしてくれる他人が、見返りもなしにすべてを注いでくれる相手が、すぐ横にいること。この男が、今ここに在ること。
抗いがたいその味。
壬生を出て彼自身のために生きてほしいと願うことも、それを拒絶されるたびに生じるわずかな安堵も確かに真実で、相反するそれらに身動きができない。
「……そろそろ、認めてください……」
ひしぎが音もなく一歩吹雪へ踏み出す。
「私が、あなたの武器として盾として在ることは、気分がいいでしょう……?」
違う、そんなことは望んでいなかった、ここまで縛りつけるつもりもなかった、ただ、生きていてほしいと、
「私が『こう』でなくなるのは、困るでしょう?」
ひたと見つめてくる瞳が、否定しようとする思考を蕩かす。
あの日の己の言葉がひしぎをここまで変えてしまったのか。それとも、ひしぎの内側に隠され身を潜ませていたものが、あの日を機に姿をあらわしたのか。
鍾乳洞の静寂の中で結晶してゆく透明な雫。ただ吹雪の望みのためだけに、鋭利なかたちに磨かれ研ぎすまされた精神。濾過され蒸留され純度を増してゆくひしぎの意志。彼の中の底知れぬ深みからひたひたと染みだし、零れ、滴り落ち、そして吹雪の胸の奥へと浸みとおってゆく意志。
この味を、一度知ってしまったら。
「もう誰も失いたくはないと、あの時そう言いましたよね。もう誰も、と」
また一歩、ひしぎが距離をつめた。この友人の性能のいい頭は一言一句を洩らさずに憶えているのだ。
「吹雪」
抑えた声が低く囁く。
「訂正してください」
誘われるように吹雪の唇が動く。
「……お前、を」
お前を失いたくない。その視線が他に注がれることを、お前が別の何かに心傾けることを、本当はもう、許せそうにない。
よくできましたとでも言いたげに、彼が隻眼を少し細めた。
<<
子供の手習いに良さそうな本はあるか、との吹雪の問いである。あらゆる種類の蔵書をためこんでいた彼の書庫ならば大抵のものはそろっているだろう、それも子供向けの本ならば特に充実していてもおかしくない、と踏んでいた吹雪の予測はおおいに外れた。
背を向けたまま手元に視線を落とし、吹雪には用途の見当もつかない器具を扱いながらひしぎは言う。
「もう随分前に、研究に必要な分を残してほとんど整理してしまいましたので……」
直射日光が入らないように塞がれた窓をちらりと見遣って、吹雪は重ねて何故だと問う。かつてはそれなりに快適な住環境であったはずのひしぎの居城は、いつからかすっかり様変わりしていた。所狭しと資料が積まれ、標本が林立し、昼だというのにあたりは薄暗い。
「必要がないからです」
無感情に、平坦な声が返る。
「私には、もう必要のないものですから。……辰伶用でしたか? それとも時人の? 申し訳ないですが、他をあたってもらえませんか」
――いつからだ。この男がこうなったのは。
真っ先に思いつく心当たりはひとつある。あれ以降、ひしぎは何かにつけて繰り返すようになった。
あの日私は誓いましたから。私はあなたに。どこまでも。地獄の底まで。
ひしぎが執拗に口に出すそのたびに、吹雪の喉元に居心地の悪さが粘りつく。
「……気に入らんな」
「何がです」
「お前のそういう姿勢がだ」
「本当に?」
作業の手をとめたひしぎが振り向いた。
「本当は、歓迎しているのではないですか?」
「……何をだ」
「私の、こういう姿勢を」
――いつから。いつからだっただろう。以前からその兆候は存在していた。姫時が逝ってから。一族の真実を知ってから。村正が去ってから。または彼自身が病を得たころから。そしてあの日、誓いを口にしてから。
ひしぎが変わってゆく。ただひとつの重要なもののためだけに、その精神から余計なものが削ぎ落とされ研ぎ澄まされる。濾過され蒸留され、ひとつの意志だけが純度を増してゆく。
何のために。
その答えを吹雪は知っている。今の彼にとってただひとつ重要なそれが、何なのかを知っている。
「私が、」
それが何なのか。
その答えを、かつてなく直接的に、ひしぎが唇にのせる。
「私があなたの望みのために生きているというのは、どんな気分ですか……?」
ひしぎはどんなことでもやってのけるだろう。吹雪の欲する未来のためなら。
「どんな気分ですか、吹雪」
時に過剰なほどのその献身は、実際問題としてありがたく心強く、その一方で不可解であり苛立たしくもあり、そしてそれは。
「……悪くないと、思っているのでは?」
それはうっすらと、後ろ暗い快さを含んでいる。
吹雪の優先順位の頂点は決してひしぎにはなり得ないのに、ひしぎのその位置には常に吹雪がいるということ。己の望みのために力を尽くしてくれる他人が、見返りもなしにすべてを注いでくれる相手が、すぐ横にいること。この男が、今ここに在ること。
抗いがたいその味。
壬生を出て彼自身のために生きてほしいと願うことも、それを拒絶されるたびに生じるわずかな安堵も確かに真実で、相反するそれらに身動きができない。
「……そろそろ、認めてください……」
ひしぎが音もなく一歩吹雪へ踏み出す。
「私が、あなたの武器として盾として在ることは、気分がいいでしょう……?」
違う、そんなことは望んでいなかった、ここまで縛りつけるつもりもなかった、ただ、生きていてほしいと、
「私が『こう』でなくなるのは、困るでしょう?」
ひたと見つめてくる瞳が、否定しようとする思考を蕩かす。
あの日の己の言葉がひしぎをここまで変えてしまったのか。それとも、ひしぎの内側に隠され身を潜ませていたものが、あの日を機に姿をあらわしたのか。
鍾乳洞の静寂の中で結晶してゆく透明な雫。ただ吹雪の望みのためだけに、鋭利なかたちに磨かれ研ぎすまされた精神。濾過され蒸留され純度を増してゆくひしぎの意志。彼の中の底知れぬ深みからひたひたと染みだし、零れ、滴り落ち、そして吹雪の胸の奥へと浸みとおってゆく意志。
この味を、一度知ってしまったら。
「もう誰も失いたくはないと、あの時そう言いましたよね。もう誰も、と」
また一歩、ひしぎが距離をつめた。この友人の性能のいい頭は一言一句を洩らさずに憶えているのだ。
「吹雪」
抑えた声が低く囁く。
「訂正してください」
誘われるように吹雪の唇が動く。
「……お前、を」
お前を失いたくない。その視線が他に注がれることを、お前が別の何かに心傾けることを、本当はもう、許せそうにない。
よくできましたとでも言いたげに、彼が隻眼を少し細めた。
<<